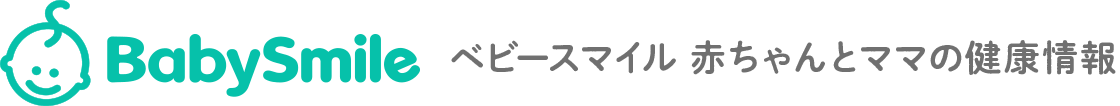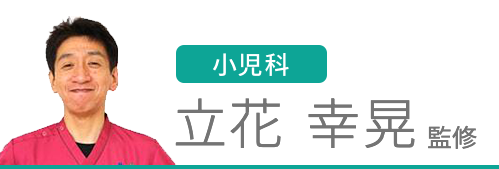赤ちゃんの健康を守るビタミンDの重要性
"くる病予防のために知っておきたいこと"
最近、赤ちゃんの「くる病」が増えていることをご存知でしょうか?
くる病は、主にビタミンDの不足によって引き起こされる病気で、特に成長期の子どもにとって深刻な影響を与える可能性があるため、赤ちゃんを育てるお母さんが正しい知識を持つことが大切です。

目次
ビタミンDと骨の健康の関係要
ビタミンDは、カルシウムやリンの吸収を助ける重要な栄養素です。これらのミネラルは骨を強くするために不可欠で、ビタミンDが不足すると、赤ちゃんの骨が正常に成長しなくなります。
くる病の症状としては、肋骨にビーズ状の突起が現れたり、足がO脚やX脚になったり、頭蓋骨が柔らかくなるなどがあります。
くる病には大きく分けて二つのタイプがあります。
一つは「代謝性くる病」で、腎臓や肝臓の病気、あるいは遺伝的要因によって起こります。もう一つは「栄養性くる病」で、ビタミンDやカルシウムの摂取不足が原因です。
特に注意が必要なのは、この「栄養性くる病」に分類される母乳育児中の赤ちゃんに起こりやすいビタミンD欠乏性くる病です。
0~5カ月児の52%がビタビンD欠乏!?
日本小児医療保健協議会(四者協)は、3月24日、「乳児期のビタミンD欠乏の予防に関する提言」を発表しました。
発表の背景として、ビタミンD欠乏乳児の増加を指摘し、0~5カ月児の52%がビタミンD欠乏だったという報告があります。
(日本小児科学会雑誌 2018; 122: 1563-1571、J Nutr Sci Vitaminol 2018; 64: 99-105)
ビタミンDは食事からの摂取と日光による生成とともによって供給されます。このため提言では、小児科医が行うべき啓発・教育活動として、以下の6項目を提示しました。
1. 胎児のビタミンD充足度は母体の充足度と比例する。妊婦だけでなく、将来を見据えて小児期・青年期からビタミンDを充足させるような生活・食事習慣を確立する
2. 母乳のビタミンD含有量は少ないが、ビタミンD充足目的で母乳栄養が妨げられることがないようにする
3. 適度の外気浴、外遊びを行い、紫外線防止のため過度に日焼け止めを使用しない
4. 補完食(離乳食)の開始を遅らせず、適切な時期に開始する
5. ビタミンDだけでなく、カルシウム(Ca)も適正に摂取する
6. ビタミンDの欠乏要因となる生活・食事習慣の改善が困難な場合は、乳児用の天然型ビタミンDサプリメントの摂取を考慮する。過剰摂取リスクを回避するためにも、説明文書の用法・用量に従い、医師の指導の下に摂取することが望まれる
赤ちゃんがビタミンD不足になりやすい理由
新生児や乳児は特にビタミンD不足になりやすい環境にあります。まず、赤ちゃんの肌はとてもデリケートなため、紫外線から守る必要があり、結果的に日光浴によるビタミンD生成が制限されてしまいます。また、排他的な母乳育児を行っている場合、食事からビタミンDを十分に補給することができません。
実際、日本での別の調査によると、3歳未満の子どもにおけるビタミンD欠乏の発生率は10万人当たり5.4人と、他の年齢層に比べて高くなっています。2005年から2014年にかけての調査ではくる病と診断される症例も増加傾向にあり、これは生活スタイルの変化と関係があると考えられます。
ビタミンD不足を防ぐための対策
では、ビタミンD不足はどうしたら防げるのでしょうか?
まず、赤ちゃんに直接ビタミンDサプリメントを与える方法です。液体タイプのサプリメントが一般的で、生後数日から始めることが推奨されています。次に、母親がビタミンDサプリメントを摂取することで、母乳中のビタミンD濃度を少し上げる方法もあります。
ただし、この方法だけでは赤ちゃんの必要量を完全に満たすことは難しいため、直接補給と組み合わせることが望ましいでしょう。
また、適度な日光浴も有効です。ただし、赤ちゃんの肌は非常に敏感なので、直射日光を避け、朝や夕方の柔らかい日光を短時間浴びる程度に留めることが大切です。日焼け止めを使用する場合は、ビタミンD生成に必要な紫外線も遮断してしまう可能性があるため、医師と相談しながら適切な方法を見つける必要があります。
ビタミンDの過剰摂取に注意
ビタミンDは不足しても問題ですが、摂りすぎにも注意が必要です。ビタミンDは確かに骨の健康を促進し、カルシウムの吸収を助ける役割を果たしますが、過剰に摂取すると体内のカルシウムレベルが異常に高くなり、骨からカルシウムが過剰に流出することがあります。これにより、本来くる病を予防するはずのビタミンDが、骨の脆弱化という、くる病に似た症状を引き起こす可能性があるのです。
また、過剰摂取すると、血中のカルシウム濃度が高くなりすぎ(高カルシウム血症)、吐き気や嘔吐、腎臓の機能障害などを引き起こす可能性があります。
赤ちゃんの健康な成長のために
くる病は予防可能な病気です。母乳育児は赤ちゃんにとって多くの利点がありますが、ビタミンDは特別な配慮が必要です。WHOの推奨を参考にしながら、赤ちゃんの成長段階に合わせた適切なビタミンD補給を心がけましょう。
大切なのは、極端に走らず、バランスを考えることです。日光浴を完全に避けるのではなく適度に行い、サプリメントも必要に応じて適量を使用する。このような総合的なアプローチが、赤ちゃんの健やかな骨の成長を支えます。
赤ちゃんの健康は、毎日の小さな積み重ねで守られています。ビタミンDについて正しい知識を持ち、かかりつけの小児科医と相談しながら、わが子に合った方法を見つけてください。健やかな成長を願って、今日からできることから始めてみましょう。
※日本小児医療保健協議会(日本小児科学会、日本小児保健協会、日本小児期外科系関連学会協議会、日本小児科医会で構成)