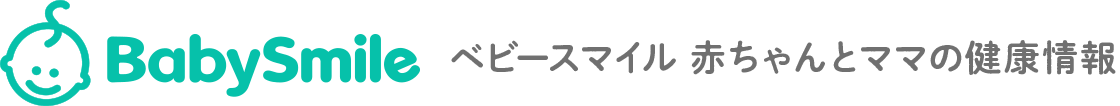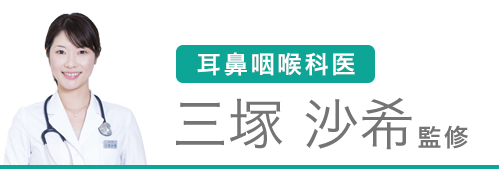離乳食

目次
離乳とは
離乳とは、赤ちゃんが母乳やミルク以外のものを口に入れられるようになり、幼児期の食事に移行する発達のプロセスです。それまで母乳やミルクなどの乳汁を吸うだけだった状態から、徐々に噛みつぶして飲みこむことができるようになります。食べる食品の量や種類が多くなり、より多くの栄養を補給して体の成長の糧となる重要な時期で、メニューや調理方法などの工夫が必要となります。
離乳の進め方については、一番重要なのは無理なく進めることで、乳児の食欲、発達などを十分に考慮することが大事です。また、将来の生活主観病の予防のためにも、健康的な食習慣を培うことも必要です。また、この離乳の時期や離乳食の与え方について、不安に思うお母さん方が多いため、離乳の基礎知識(離乳の時期や方法)や、離乳食時に与えたい栄養分についてご紹介します。

離乳の開始時期
| 時期: | 生後5~6ヶ月頃 |
| 発達段階: | 首がすわってくる 支えると座れる 食べ物に興味を持つ スプーンなどを口に入れても舌で押し出さなくなる(哺乳反射が減少する) |
| 注意事項: | 離乳前に果汁などを与えない(※1) スプーンの使用は離乳後で良い(※2) |
※1:離乳前の乳児にとって一番の栄養源は乳汁(母乳もしくはミルク)で、離乳の開始前に果汁などを与えることで乳汁の摂取が少なくなり、タンパク質、脂質、ビタミン類やミネラルが不足する可能性があるため。
※2:哺乳反射が減少する前にスプーンなどを使用すると、舌で押し戻すなどして上手に与えることができない。
離乳食の進め方
ゴックン期(5~6ヶ月頃)
口を閉じてごっくんと飲み込む練習をする。味や食感に慣れる。
| 回数 | 1日1回 | |
| 授乳 | 赤ちゃんが飲みたいだけ | |
| おかゆ | 10倍かゆ | |
| かたさ | なめらかですりつぶされた状態 | |
| 味付け | しない(だし程度はOK) | |
| 食材 | 炭水化物 | 米、麺類(うどん、そうめん)、食パン、いも類(じゃがいも、さつまいも) |
| ビタミン・ミネラル | 根菜類(にんじん、大根、かぶ、たまねぎ) | |
| 葉物(ほうれん草、小松菜、キャベツ、白菜、レタス) | ||
| 野菜(かぼちゃ、トマト、ブロッコリー、とうもろこし) | ||
| 果物(りんご、みかん、いちご、桃、メロン、すいか、バナナ) | ||
| タンパク質 | 豆腐、しらす、じゃこ、白身魚(ひらめ、かれい) | |
| 調味料 | だし | |
[ ポイント ]
栄養は母乳とミルクから摂取できているので食材の種類や量は気にしなくて良い。
スプーンや食事の雰囲気に慣れることを重視。
いやがる時は無理に与えない。
食材はアレルギーの少ないものから少しずつ増やす
栄養は母乳とミルクから摂取できているので食材の種類や量は気にしなくて良い。
スプーンや食事の雰囲気に慣れることを重視。
いやがる時は無理に与えない。
食材はアレルギーの少ないものから少しずつ増やす
モグモグ期(7~8ヶ月頃)
もぐもぐと口を動かして、食べ物をつぶして飲み込む練習をする。
| 回数 | 1日2回(母乳・ミルクの前に与える) | |
| 授乳 | 赤ちゃんが欲しがる時(1日5~6回が目安) | |
| おかゆ | 7倍かゆ | |
| かたさ | 舌でつぶせるかたさ(豆腐くらい) | |
| 味付け | ごく薄味(だしなどで風味づけ程度) | |
| 食材 | 炭水化物 | 米、麺類(うどん、そうめん)、食パン、いも類(じゃがいも、さつまいも、里芋) |
| ビタミン・ミネラル | 根菜類(にんじん、大根、かぶ、たまねぎ) | |
| 葉物(ほうれん草、小松菜、キャベツ、白菜、レタス) | ||
| 野菜(かぼちゃ、トマト、ブロッコリー、とうもろこし、アスパラガス、えんどう豆、なす、きゅうり、青のり) | ||
| 果物(りんご、みかん、いちご、桃、メロン、すいか、バナナ、なし) | ||
| タンパク質 | 豆腐、しらす、じゃこ、白身魚(ひらめ、かれい、たら、鯛、鮭、めかじき、ツナ)鶏ささみ、納豆、粉チーズ、卵黄(卵白は8ヶ月以降)、きなこ | |
| 調味料 | だし、塩、しょうゆ、みそ | |
[ ポイント ]
離乳食から30~40%程度栄養を摂取する時期となるため栄養のバランスを考えて与える。
好き嫌いや急に食べなくなることがあるが焦らず無理せず与える。
味を濃くすると食欲が増すことがありますが、味覚が育ちにくくなるためできるだけ食材の味を生かして調理する。
離乳食から30~40%程度栄養を摂取する時期となるため栄養のバランスを考えて与える。
好き嫌いや急に食べなくなることがあるが焦らず無理せず与える。
味を濃くすると食欲が増すことがありますが、味覚が育ちにくくなるためできるだけ食材の味を生かして調理する。
カミカミ期(9~11ヶ月頃)
歯茎で食べ物をかむ練習をする時期。3回食になり食事のリズムもできてきます。
| 回数 | 1日3回(母乳・ミルクの前に与える) | |
| 授乳 | 赤ちゃんが欲しがる時(1日5~6回が目安) | |
| おかゆ | 5倍かゆ | |
| かたさ | 歯茎でぶせるかたさ(バナナくらい) | |
| 味付け | ごく薄味(ごく少量の調味料や油) | |
| 食材 | 炭水化物 | 米、麺類(うどん、そうめん、スパゲッティ)、食パン、いも類(じゃがいも、さつまいも、里芋、やまいも) |
| ビタミン・ミネラル | 根菜類(にんじん、大根、かぶ、たまねぎ、ごぼう) | |
| 葉物(ほうれん草、小松菜、キャベツ、白菜、レタス、春菊、長ねぎ、ちんげん菜、もやし) | ||
| 野菜(かぼちゃ、トマト、ブロッコリー、とうもろこし、アスパラガス、えんどう豆、なす、きゅうり、青のり、ピーマン、きのこ、ひじき) | ||
| 果物(りんご、みかん、いちご、桃、メロン、すいか、バナナ、なし、ドライフルーツ) | ||
| タンパク質 | 豆腐、しらす、じゃこ、魚介類(ひらめ、かれい、たら、鯛、鮭、めかじき、ツナ、青魚、ほたて貝柱水煮缶)、豚肉、牛肉、鶏肉(ささみ、ひき肉)、レバー、納豆、プロセスチーズ、粉チーズ、卵、きなこ | |
| 調味料 | だし、塩、しょうゆ、みそ | |
[ ポイント ]
離乳食から半分以上の栄養を摂取する必要があるため、栄養バランスが重要となる時期。
生活習慣に慣れるためにも、毎日同じ時間に食事をすることが望ましい。
食べる量に個人差があるので、1日ではなく5~7日程度でバランスをとるようにする。
好き嫌いで食べない時は無理強しなくて良い。別の日に出すと食べることもある。
大人の食事を取り分けて調理したりベビーフードも取り入れて無理なく進める。
自主性も大切にして、自分から食べ物に手を出すようになったら手で持って食べられるものも用意する。
離乳食から半分以上の栄養を摂取する必要があるため、栄養バランスが重要となる時期。
生活習慣に慣れるためにも、毎日同じ時間に食事をすることが望ましい。
食べる量に個人差があるので、1日ではなく5~7日程度でバランスをとるようにする。
好き嫌いで食べない時は無理強しなくて良い。別の日に出すと食べることもある。
大人の食事を取り分けて調理したりベビーフードも取り入れて無理なく進める。
自主性も大切にして、自分から食べ物に手を出すようになったら手で持って食べられるものも用意する。
パクパク期(12~18ヶ月頃)
大人に近い食事がとれるように徐々にしていく時期。授乳も回数を減らし卒乳します。
| 回数 | 1日3回の離乳食と1~2回の捕食(おやつ) | |
| 授乳 | 次第に減らしていく | |
| おかゆ | 軟飯~ごはん | |
| かたさ | 歯茎でかめるかたさ(ゆで卵の白身や肉団子ていど) | |
| 味付け | 薄味(少量の調味料や油) | |
| 食材 | 炭水化物 | 米、麺類(うどん、そうめん スパゲッティ)、食パン、いも類(じゃがいも、さつまいも、里芋、やまいも)、中華乾麺、ビーフン、春雨、蒸しパン、マフィン |
| ビタミン・ミネラル | 根菜類(にんじん、大根、かぶ、たまねぎ、ごぼう) | |
| 葉物(ほうれん草、小松菜、キャベツ、白菜、レタス、春菊、長ねぎ、ちんげん菜、もやし) | ||
| 野菜(かぼちゃ、トマト、ブロッコリー、とうもろこし、アスパラガス、えんどう豆、なす、きゅうり、青のり、ピーマン、きのこ、ひじき、セロリ、たけのこ、アボカド、かんぴょう、きくらげ) | ||
| 果物(りんご、みかん、いちご、桃、メロン、すいか、バナナ、なし、ドライフルーツ、くだもの缶詰) | ||
| タンパク質 | 豆腐、しらす、じゃこ、魚介類(ひらめ、かれい、たら、鯛、鮭、めかじき、ツナ、青魚、ほたて貝柱水煮缶、貝、たらこ、干物、桜えび)、豚肉、牛肉、鶏肉(ささみ、ひき肉)、レバー、納豆、プロセスチーズ、粉チーズ、卵、きなこ、はんぺん、ハム、卵豆腐 | |
| 調味料 | だし、塩、しょうゆ、みそ、ゴマ油、カレー粉、マヨネーズ、ケチャップ | |
[ ポイント ]
食べられるものが多くなり、大人の食事を取り分けで準備でき負担が減りますが、反面、「好き嫌い」や「ムラ食い」「ばっかり食べ」などの癖で悩む時期。
子どもが食べなくても、いろいろな食材を準備し視覚で慣れさせたり抵抗感をなくしましょう。
1回に食べられる量が少ないため、おやつは必要です。お菓子ではなく、果物、いも類、乳製品など食事の補完となるものを選びます。
自主性を育てるために、手づかみで食べられるものや、スプーンやコップなどの食器も自分で持たせ、出来るだけ自由にさせます。
食べられるものが多くなり、大人の食事を取り分けで準備でき負担が減りますが、反面、「好き嫌い」や「ムラ食い」「ばっかり食べ」などの癖で悩む時期。
子どもが食べなくても、いろいろな食材を準備し視覚で慣れさせたり抵抗感をなくしましょう。
1回に食べられる量が少ないため、おやつは必要です。お菓子ではなく、果物、いも類、乳製品など食事の補完となるものを選びます。
自主性を育てるために、手づかみで食べられるものや、スプーンやコップなどの食器も自分で持たせ、出来るだけ自由にさせます。