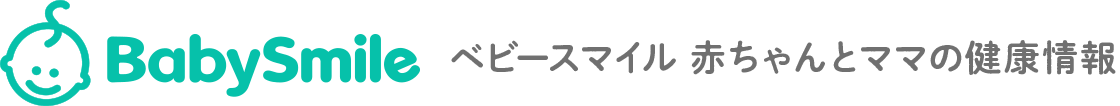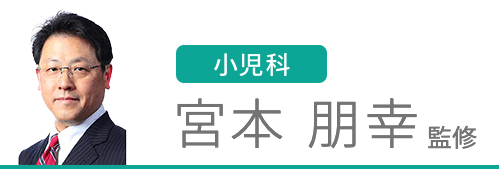放置すると危険な赤ちゃんの「鉄欠乏性貧血」

赤ちゃんが最近、活気がなくいつも眠そうだったり、遊びたがらない、顔色が悪い、疲れやすいなど気になることはありませんか?そんな時には鉄欠乏性貧血症が疑われます。
赤ちゃんと「貧血」という言葉がなかなか結び付かない方もいるかもしれませんが、意外に知られていないことなので解説してみます。

目次
赤ちゃんの貧血について
赤ちゃんの貧血も、基本的には大人の貧血と同じです。血液中の赤血球が不足し、体内に酸素を十分に運べなくなる状態を指します。ただ、赤ちゃんの成長や発達に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早期発見と適切な対応が大切です。
鉄欠乏性貧血とは?
赤ちゃんの貧血の中で最も多いのが「鉄欠乏性貧血」です。赤血球を作る材料となる鉄分が不足することで、酸素を運ぶ赤血球の数が減少してしまいます。出生時には赤ちゃんの体に胎児期から蓄えられていた鉄が十分にありますが、生後4~6カ月頃には使い果たしてしまいます。その後、母乳やミルク、離乳食から十分な鉄分を摂取しないと貧血が進行する可能性があります。
この貧血は、生後6カ月から1歳頃の急速な成長期に特に起こりやすく、離乳食の内容や鉄分の摂取量が不足することが主な原因となります。
また、早産児や低出生体重児は生まれつき体内の鉄の蓄えが少ないため、鉄欠乏性貧血になりやすい傾向があります。さらに、妊娠中にお母さんが鉄分不足だった場合、赤ちゃんにもその影響が及ぶ可能性があります。これらの要因が重なることで、赤ちゃんの体内に必要な鉄分が不足し、貧血の症状が現れるのです。
鉄欠乏性貧血の症状
鉄欠乏性貧血の症状は、軽度では分かりにくい場合もありますが、注意深く観察することでいくつかの兆候に気づくことができます。
赤ちゃんの顔色が青白く見えたり、元気がなく動きが少なくなることが一般的な症状です。周りの子と比べて、顕著に色白だなと思う時は、一度かかりつけのお医者さんに相談してみましょう。
ただ、鉄欠乏性貧血の場合は、徐々に貧血が進行し、症状として顔の血の気が少ないというくらいの症状しか出ないことも多いのです。かかりつけの先生と予防接種や健康診断の時などによくコミュニケーションをとりながら、お子さんの健康を守っていきましょう。
他にもある赤ちゃんの貧血
赤ちゃんに起こる貧血は鉄欠乏性貧血だけではありません。以下のような種類の貧血も考えられます。
1.溶血性貧血
赤血球が通常より早く破壊されることによって起こる貧血です。新生児溶血性疾患(母体と赤ちゃんの血液型の不一致)や、赤血球の形に異常がある遺伝性疾患が原因となることがあります。この場合、鉄欠乏性貧血と同じような兆候に加え、出生後早期から黄疸が強くみられます。血液型不一致の場合の黄疸は新生児時期のみで解決しますが、遺伝性疾患は長引く黄疸が特徴です。
2.未熟児貧血
早産や低出生体重児では、赤血球の生成能力が未熟であることや、体内の鉄分の蓄えが少ないことを背景に急激に身体が成長するため赤血球の産生が追い付かなくなり、貧血が起こりやすい傾向があります。
これらの貧血はそれぞれ異なる原因によって引き起こされますが、いずれも早期発見と適切な治療が重要です。
貧血の重症化によるリスク
貧血が重症化すると、赤ちゃんの成長や健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。貧血が重度に進むと、身体に十分酸素を運べるように心臓が普通よりたくさん働かなくてはならず、心臓に負担がかかり、そのうち心臓が疲れて心不全となることがあります。
貧血の予防と対処法
赤ちゃんの貧血を予防するためには、適切な栄養の摂取が重要です。特に離乳食が始まる時期には、鉄分を多く含む食品を意識的に取り入れることが大切です。例えば、レバー、赤身の魚、ほうれん草、大豆製品(豆腐や納豆)などを離乳食に加えましょう。また、鉄の吸収を助けるビタミンCを含む野菜や果物を一緒に摂取することで、より効果的に鉄分を補えます。
母乳のみで育てている場合には、鉄分を含む離乳食を意識的に取り入れることも有効です。また、早産児や低出生体重児などリスクが高い赤ちゃんについては、小児科医の診察を受けることで、適切なサポートが受けられます。
貧血が疑われる場合には、医師に相談し、必要に応じて血液検査を行いましょう。場合によっては鉄剤の処方や栄養指導が行われます。
鉄分を強化した離乳期用のミルクも販売されているので、それを利用するのも一つの方法です。
お母さんへのメッセージ
赤ちゃんの貧血は、適切な対応を行えば改善が期待できる病気です。普段の生活で赤ちゃんの様子をよく観察し、元気がない、顔色が悪い、食欲が落ちているなどの兆候に気づいたら、早めに小児科医に相談してください。赤ちゃんが健やかに成長するためには、毎日の食事や栄養に気を配ることが大切です。